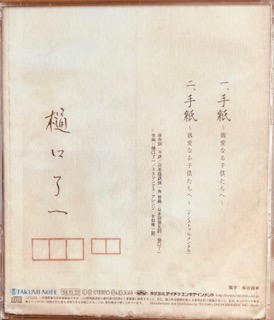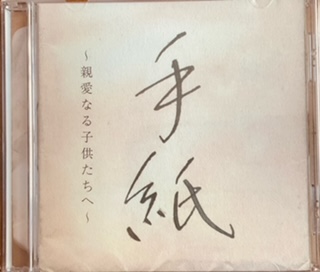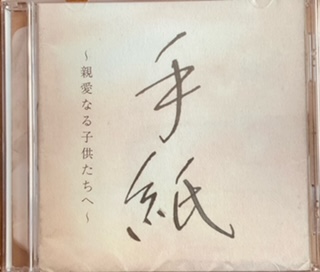
昨年の10月、母を亡くした。88歳だった。もともと高血圧や痔疾、変形性膝関節症などの疾患を抱えていたが、春ごろから体力、気力、食欲の低下が進んだ。
一日中横になることが多くなり、処方薬もかかりつけ医から私が受け取るようになった。
粗相の回数も増えてきた8月、浴室で汚れを落としている間に多めの下血があった。もはや痔疾の症状ではないと思い、緊急入院させた。入院して初めて、大腸に穴が開いていることがわかった。手術に耐えるだけの体力もなく、すでに手遅れだった。
私がシンガーソングライターの樋口了一さんの歌“手紙 親愛なる子供たちへ “に出会ったのは、今から12年前のこと。介護される老親から我が子に宛てた手紙の歌だが、テレビから聞こえてきたその歌詞にすぐさま惹きつけられた。
当時の母は、毎日「あそこが痛い」「ここが悪い」と訴えてはいた。介護が必要な段階でこそなかったが、毎日、それも食事中などに同じことを聞かされていると、さすがにうんざりすることもあった。
そんな折に聞こえてきた「あなたと話す時 同じ話を 何度も何度も 繰り返しても その結末をどうかさえぎらずにうなずいて欲しい あなたにせがまれて繰り返し読んだ絵本のあたたかな結末は いつも同じでも私の心を平和にしてくれた」の歌詞が、私の心に突き刺さった。
そして、12年後。母は旅立って行ったが、ずっとそばにいた者として、「なぜ、もっと早く気づいてあげられなかったのか」と自分を責めた。
2周忌も終えたある日、久しぶりにあの「手紙」を聞いてみた。改めてすべての歌詞が重くのしかかってきたが、とりわけ心に染み入ったのが、「私の人生の終わりに少しだけ付き添って欲しい」のくだり。
果たして私は、母の「人生の終わりに少し」でも「付き添」うことができたのだろうか。
宮本 威